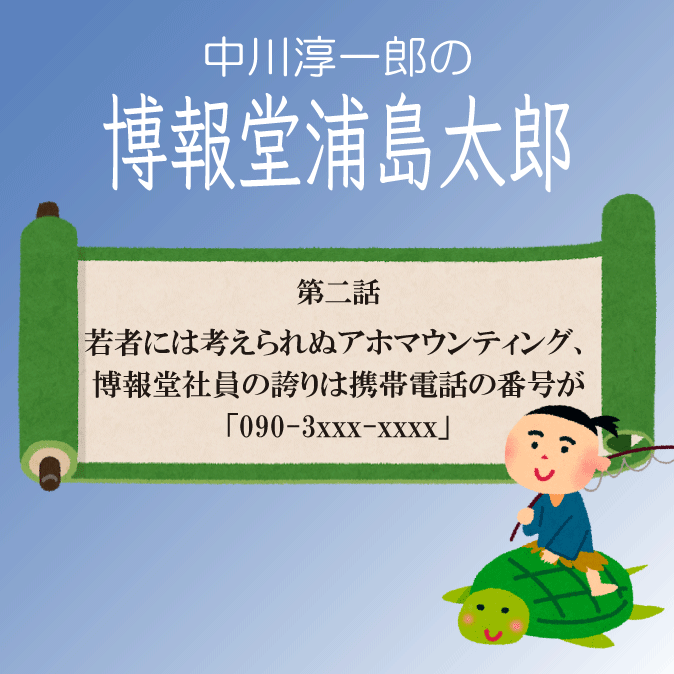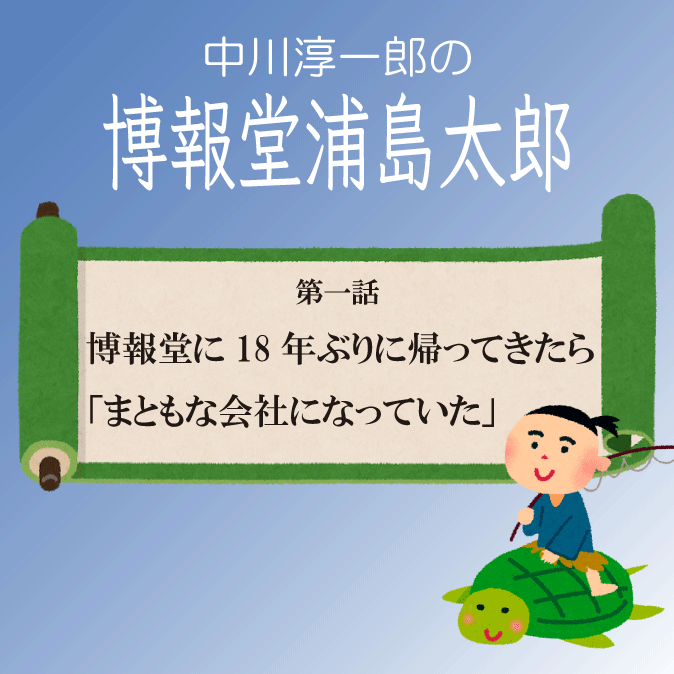先日、博報堂PR局の研修に参加しました。内容は、某外資系企業の日本上陸と日系企業のコラボレーションを発表する模擬記者会見を行うというものです。PR局の若手(経験2年以内)が午前中からベテラン社員の講義を受けたのち、会見の演出案を考えたり、自分が登壇して話す内容を作り、想定Q&Aも作っていざ本番(というか模擬会見)に臨むというものです。
私はこの会見の記者役として参加しました。経済部の記者はけっこう厳しい質問をしたりするものですが、現在博報堂社内プロジェクト「風の間」メンバーであるヨッピーさんと弊社のY嬢、そしてテレビの放送作家と2人のフリーライターも同じく記者役として参加しました。
今回の登壇者の中には、他の職種から異動してきた人もいて、社会人としてはそこそこのベテランのため、切り返しも上手で「これだったらキチンとPR業務をクライアントのためにやれそうだな」なんてエラソーに思ったりもしました。
かつて私がCC局(コーポレートコミュニケーション局=PR局の前身)にいた時はクライアント企業向けに「メディアトレーニング」をやることはありました。何らかの不祥事が起きた場合にいかにして会見をするか、というのを半日がかりで行う研修です。この研修はあくまでも博報堂の「商品」の一つですが、今、なぜ若手社員がこのような研修を社内でやるのかを聞いたら「なるほど」と思いました。
「私達はクライアントの記者会見をサポートすることはよくありますが、楽しげな演出や資料作り、会場の設営はやるものの、実際に記者の前に立ち、厳しい質問を受けるのはクライアント。その気持ちもちゃんと理解しなくてはいけないな、と考えました。記者会見の仕事を受けるにあたっても、当事者意識を持つ必要があると考えたので、こうした研修をやっているのです」
これはクライアントあっての広告会社、という立場においては実にまっとうな考えです。広告会社から事業会社に移った人は「こんなに大変だとは思わなかった」なんて言うこともあるわけで、この研修は非常に有益といえましょう。
さて、研修といえば、私も博報堂時代、印象深い研修がありました。1998年末、組織改編があり、若手中心の「情報デザイン2部」という部署に所属することになったのですが、同部には3つの「グループ」がありました。グループリーダーは1983年入社(当時38歳)のI氏、1984年入社(37歳)のT氏の2人に加え、1988年入社(35歳)のM氏がいました。
私はM氏のグループに入りましたが、このグループは他の部署から「お子ちゃまチーム」と呼ばれていました。なにしろリーダーは2浪していたとはいえ、最年少。メンバーも、1991年入社の30代前半の2人がいるものの、その他は局内最年少の私(25歳)と1つ上のY先輩(25歳)です。他のグループは脂の乗った30代中盤の社員もたくさんいる中、明らかに我々は若かった。
だからこそ、局の大事な会に出た時にも、Mリーダーは諸先輩が居並ぶ中、若干「お手並み拝見ですな、ガハハ」的な扱いを受けていたのだと思います。
さて、話は本筋である研修の話になりますが、2ヶ月か3ヶ月おきに1つの実在商品を題材としたPRのプレゼンを3つのグループがすることになりました。本当に良い提案は、実際にクライアントに自主プレゼンすることも目指します。全3回のこの研修、まさに「社内競合プレゼン」のようなもので、同商品を担当する営業担当者も審査員として「どのグループの提案がもっともクライアントのためになるか」を検討し、誰が勝利するかが決まります。
1回目の時は某外資系小売店を想定クライアントとしましたが、これは老獪な最年長リーダー・I氏のグループの勝利に終わりました。その晩は我々5人は口惜しさのあまり飲みに行き、傷をなめ合うのでした。この時のプレゼンテーターは私です。企画は良かったのかもしれませんが、当時の私は「喋り方教室に行きなさい」と局長から言われるほど喋りがヘタクソで、プレゼンも当然ヘタだったのでそのせいで負けてしまったのかもしれません。
そして2回目、今度の想定クライアントは某出版社です。いかにして文庫キャンペーンを盛り上げるか、という提案をすることになったのですが、私がたまたま“Bibliotherapy”という言葉をネットでみつけました。日本語に訳すと「読書療法」ですが、「読書をすれば賢くなる」といった解釈もできるようです。我々はこれを日本に広めることを考え、同社がそこに協賛する形を取ればいいし、広告表現もこれに則ればいい、といった提案をコアアイディアとしました。
この「ビブリオテラピー」の権威はアメリカの「ロバート・ビーランド教授」ということも分かり、私は「日本の文庫本を売るためにビーランド先生の講演会を日本で開くことは可能ですか?」とご本人にメールを書いたところ、なんとご本人から返事が来た!
恐らくhakuhodoという企業ドメインからメールが来ている以上、ある程度信頼がおけるかもしれないとビーランド先生は考えてくれたのかもしれません。「YOU達の問題意識はいいな。協力してやってもいいぜ(意訳)」と先生から返事が来た時は我々のグループは大興奮!
さらに、私は日本における「読書療法」の専門家である大学教授とも会うことにしました。山口県の大学の先生だったのですが、京都で講演会があるとのことで京都まで会いにいきました。
かくして、「協力者が続々と出てきています!」といったことも含め、私の1つ上の先輩・Y氏がプレゼンをしました。結果は勝利! しかし、Mリーダーは喜ぶそぶりを一切見せません。むしろ憮然としています。恐らく喜ぶことが失礼だと感じ、他チームへの配慮があったのでしょう。
その晩、当然の如く我々は再び酒を飲みに行くのですが、この時ようやくMリーダーは相好を崩し、今回の勝利を心から喜んだのです。M氏は何度も「オレら『お子ちゃまチーム』とか言われても勝ったよな! これって気持ちいいよな!」と何度も言い、我々部下は「Mさんのリーダーシップあってこそです!」と楽しい宴となりました。

そして最後の研修、これまで2つのチームが勝利したため、まだ勝っていない唯一のチームが本気でプレゼンをしてくることは予想できていました。お題は忘れてしまいましたが、我々は連日のように通常業務終了後、企画書作成のため残業をしていました。そして本番前日、Mリーダーは我々全員を会議室に呼び、真剣な表情を浮かべこう言いました。
「オレは勝ちたい」
我々はその迫力に何も言えません。
「前回オレらは勝った。でも、今回勝たなくては意味がない。3回のうち2回勝てばオレらの圧勝ということになる。他のチームは『研修なのに本気になってあいつらはアホか』と思っているかもしれないが、オレは本気でやりたい。頼む。4人の力を貸してくれ」
私は『半沢直樹』(TBS系)をはじめとしたビジネス系ドラマは「ケッ、大袈裟なんだよ。そんな熱いビジネスマンなんていねーよ」などと思うものですが、この時のMリーダーの熱さは本物でした。
我々は「はい、Mさん。やります。勝ちましょう」と誓い合い、翌日のプレゼンに臨みました。各チーム、最後のプレゼンにはエース格を送り込んでくる。我々もプレゼン上手として知られ「おにいちゃん」的役割を果たしていた31歳のE氏を送り込みます。このプレゼンの結果はその後選考委員の協議のもと夕方に発表されることになっていました。
プレゼン終了後、私はMリーダーと一緒にクライアントの記者会見の現場に夕方から行っていました。東京・青山のスパイラルホールでの発表会がパーティーに移った時、Mリーダーの携帯電話が鳴りました。
「おぉ、おぉ、そうか…」
相手はE氏だったようですが、M氏は記者会見の現場に突然やってきた電話ということで淡々と対応します。そして小さくガッツポーズをした。
「どうしたんですか?」
「勝った。今のはEからの電話だ。オレらは2回勝った。ここまで時間がかかったのは甲乙つけがたく審査員が迷ったからだと思うけど、オレらが勝った」
当然のようにこの晩も5人で祝杯をあげましたが、「オレは勝ちたい」というプレゼン前夜のMリーダーの姿は自分が仕事人として真摯に取り組むにあたっての規範となっています。今の社内研修にしても、こうした「イズム」が感じられ、今回参加して本当に「いい時間だった」と思いました。
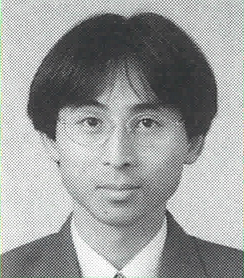
1973年東京都生まれ。ネットニュース編集者/PRプランナー。一橋大学卒業後、博報堂入社。企業のPR業務に携わる(2001年退社)。著書に『ウェブはバカと暇人のもの』『ネットのバカ』など。
(写真は1997年入社時)