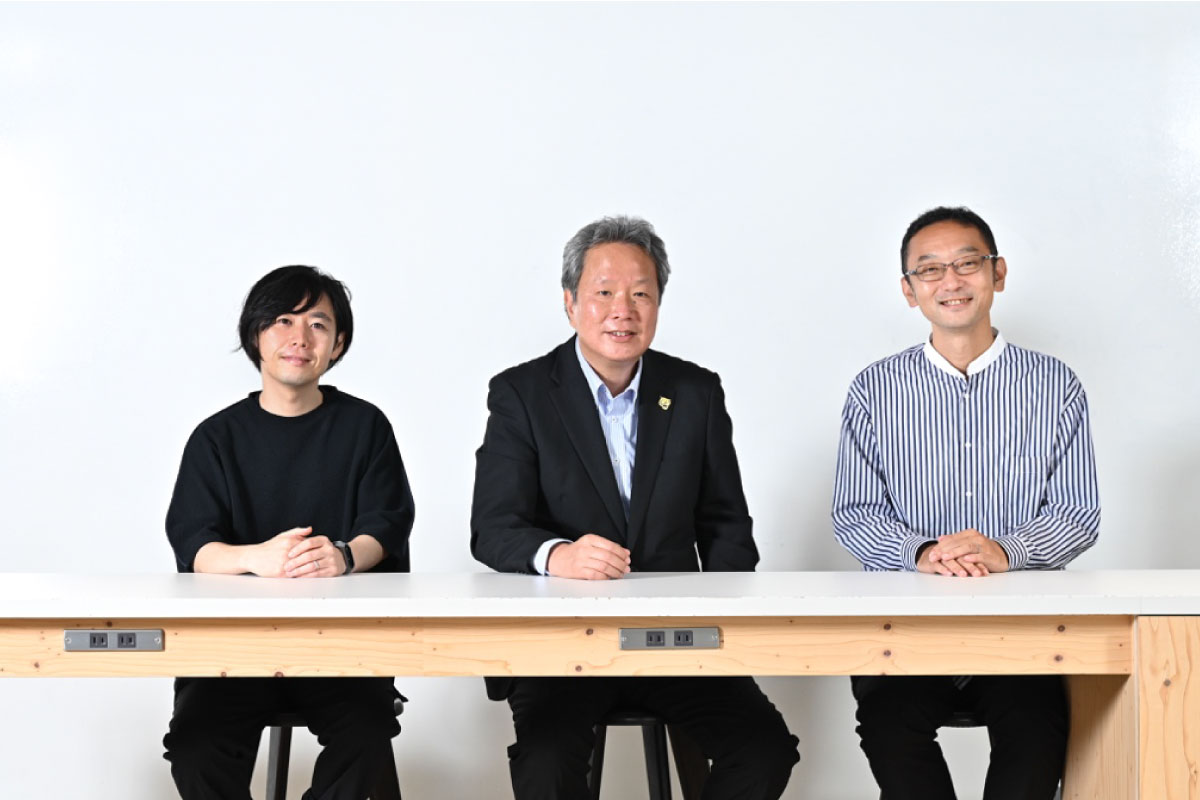

木下
まずは自己紹介をお願いします。
山本
阪急阪神ホールディングスのグループ開発室で、グループのDXを担当している山本です。最初は阪神電気鉄道に入社し、電気部門で保守や電気工事を20年程経験しました。鉄道の安全とダイヤを守ることが役割の仕事です。その後、グループのIT子会社であるアイテック阪急阪神に移り、東京に転勤になりました。アイテック阪急阪神では、東京の鉄道会社を中心にネットワーク監視系のシステムを構築、販売していました。営業と技術を兼ねたような役割でした。2020年4月に阪急阪神ホールディングスに移り、今の立場になりました。

木下
阪神電車では新しい電車の運行管理システムを構築したと伺いました。
山本
阪神電車は本線が約33キロと短いのですが、駅は33駅もあります。そのため昭和40年代からネットワークを使って合理化する取り組みを始めており、無人駅もあるんです。阪神が培った鉄道系のシステムは先進的なものだったので、外販したところ東京の多くの電鉄会社にご導入いただけたんです。
木下
近年はDXという言葉が盛んに使われるようになりましたが、山本さんは東京に移られた時点で既にDXをビジネスにされていたということですよね。では、デジタル甲子園について教えて下さい。始められたきっかけは何なのでしょうか。

山本
阪急阪神グループはリアルインフラをオペレーションする企業体です。鉄道、不動産、オフィス、商業施設などがあり、これらのビジネスは今後少子高齢化が進むと売り上げが減ってしまいます。そうした流れにおいても収益が得られる体制に変わっていけるよう、DXを進めているところです。DXについて考える中で、「これまではあまりITサービスを手がけてこなかったので新しく作ろう」、「エンタメビジネスをやっている我々らしい、楽しいITサービスをやりたい」という話になりました。そこで、最初はグループの象徴的施設である甲子園のデジタル化がふさわしい、ということになったんです。
木下
私も阪神タイガース好きでよく甲子園に行っていたので、デジタル版が出来ると伺い、新しい体験が生まれる可能性を凄く感じました。どんな風にサービスを構想したのでしょうか。
山本
我々がリアルインフラのオペレーターであることは、デジタルになっても弱みではなく強みになると思っています。甲子園ではタイガースの試合、高校野球、コンサートなどをやっているので、デジタル化した場合でもまずリアルと同じことはやれるようにしたいと考えました。将来的にはデジタルだからこそ出来ることにも取り組んでいきたいと思っています。
今回開催したデジタル甲子園は企業展示会であり、「甲子園のデジタルスペースをお貸しするので商品を展示、商談して下さい」というのがコンセプトです。デジタルなので、アプリも使えるようにしなくてはいけないと考えまして、出展企業のご要望に応じて用意しています。2021年3月に第一回を開催し、今後に向けてビジネススキームを含めてさらに作り込んでいきます。
木下
スタジアムなどのエンタメ施設は、持ち主と興行主が分かれていることが多く、それがデジタルツインを作る際の課題になることが多くあります。阪急阪神ホールディングスは甲子園について、そのどちらでもあることが強みかなと思います。
山本
持ち主も興行主も直営グループの中にいるので、ホールディングスが話を事業部門に持ち込んで承認がもらえればサービスが可能になります。スケジュール的には、デジタルツインという言葉が社内で最初に出たのが2020年の6月でした。9月には甲子園で3Dアバターを動かそうという話になり、そこから作り始めて2021年3月の展示会に間に合わせました。51ブース、93社にご参加いただきました。
目黒
それ程のスピード感で進めることが出来た理由は何なのでしょうか。大企業でかつ社会インフラを扱う企業となると、いくら自社グループ内の調整とはいえ確認や稟議に時間がかかってしまうケースも少なくないと思ったのですが。

山本
DXを絶対遂行しなくてはいけないという、トップの強い思いがあると思います。2020年度決算の最終損益は赤字となりましたし、出来るだけ早く形にすることが求められていました。スピードの点で言うと、甲子園を所管する事業部門と協力いただいたシステム開発会社も素晴らしかったです。精力的に動いていただき、「ものづくり日本の根性を見た」と思いました。
目黒
新しいものを一早く取り入れられるその社風はどういったところから来ているのでしょうか。
山本
阪急も阪神も新しいものを作って来た歴史があると思います。私の出身母体である阪神は先ほどお話した通り、鉄道運営の情報ネットワークをいち早く作りました。まだプロ野球がない大正時代に、5万人が観戦できる甲子園球場も作っています。阪急は世界に類を見ない民鉄経営モデルを構築しました。鉄道を核として不動産、百貨店、レジャー施設を運営する多角経営モデルです。明治時代には宝塚温泉郷を大規模に開発して宝塚歌劇団も作っています。甲子園も宝塚も、作られた当時は誰も見たことがない、夢の世界だったと思います。これから我々が作るデジタル世界も、誰も見たことがない、体験したことがないものにしたいと思っています。
プロトタイプでも体験する場をつくったことで次の課題が早く発見できたことが収穫
木下
デジタル甲子園のプラットフォームとしての特徴を教えてください。また今回monoAIさんを協業プレイヤーに選ばれたと思いますが、どのように選定したのですか。
山本
3Dのプラットフォームを開発している会社を調べたときに、3Dの世界でアバターを動かせるものは他にもあったんです。今のプラットフォームを選ぶ一番の決め手になったのは、オープンであることですね。プラットフォームによっては、3Dの世界の中で開発会社しか建物を建てられないようなものもありました。そうではなくて、運営している開発会社に頼らなくても自由にいろいろ作れるようなものがいい、と考えてプラットファームを決めました。

木下
沢山の人が接続した際に、しっかりと動くことも重要になりますよね。
山本
はい、ネットワーク回りもポイントでした。同時接続が10~100人程度としているものもあった中で、我々が選んだシステムはサーバーを追加するだけで同時接続数を柔軟に増やすことが出来たんです。今現在は一つのサーバーで約1000人に対応しています。
木下
第一回のイベントを実際に開催してみていかがでしたか。
山本
システムをしっかり動かすことが出来ましたし、出展企業への営業、フォローもある程度上手くいったと思います。失敗したのは集客でした。デジタル甲子園という名前でビデオをアップしていれば、多くの人に関心を持ってもらえるだろうと甘い見通しを立ててしまいました。来場者は、関係者を除くと三日間のトータルでのべ1600人ほどでした。そこについて出展企業は大変ご不満だったと思います。一方で、「物理的に離れた場所にいる人と、同じ空間で商談出来ることはとても面白い」とご評価をいただくことも出来ました。
木下
当社も出展させていただき、目黒は実際にブースに立っていました。

目黒
知らない方とお話をする際、3D空間でありながらも同じ空間にいてその場を共有している感覚があるので、とても話しやすかったですね。また今回は自分専用のアバターではありませんでしたが、自分と同じ姿のフォトリアルアバターや、自分の好きなキャラクターアバターが選択できるようになると空間内のコミュニケーションはもっと活発になりそうです。
山本
課題が出るだろうというのは認識していましたが、そういったご意見を伺いたくて早く1回目を開催したので嬉しいですね。普通のスピードで開発していたら、少なくとも3カ月程度は開催が遅くなったはずなので、まだ改善点には気づけていなかったはずです。やってみないと分からないことが多いと本当に感じます。9月の第二回に向けて、アプリの改善など様々な取り組みを進めています。
木下
従来であれば、一度批判されると継続が難しくなってしまうと考えて、しっかりとした完成品を作るのが一般的でしたよね。そうではなく、アジャイル的な考え方でこれだけ大規模なプロジェクトをやっている例は日本にはあまりないと思うのですが、本来あるべき姿だと感じています。今後デジタル甲子園を一歩前に進めていく際にリアルの場とバーチャルの場を連携させる形での新たな接点づくりとして今考えていることはありますか。
山本
まだそこが考えられていません。今はリアルの再現に取り組んでいて、ある程度リアルと同じことが出来るようになってきました。でも当然ながらリアルでしか出来ないことは沢山あります。デジタルについても“デジタルツイン”というくらいですから、デジタルでしか出来ないことが作れてこそ、やっとリアルと対等になると思うんです。それが出来ないと、いつまでたってもリアルとデジタルは上下の関係でしかなくなってしまいます。
木下
第二回について教えていただけますか。
山本
9月7〜10日に開催するのですが、テーマを「DXが変革するマネジメントのあり方やエンタテインメントの世界」としました。我々の事業の中でエンタテインメントは大きな柱の一つです。収益系のDXを論じる際、企業経営とエンタメという一見違うものを一つのイベントで表現するのが我々らしいかな、と考えました。
木下
DXはBtoBや業務効率化の話になりやすいので、エンタテインメント業界でどういったエクスペリエンスが新たに生まれるのか興味深いですね。
山本
今回新たに機能として盛り込んだのがセミナー機能です。リアルの展示会であればセミナーがあるので、それをデジタルでも出来るようにして前面に押し出しています。セミナーにご登壇いただく方には、マネジメントとエンタメを共存させる意義を私から説明させていただいて、共感いただいています。おそらく、とても興味深いセミナーになるのではないかと思います。
木下
第二回の開催に当たっての抱負をお聞かせください。
山本
今回追加したセミナーについても、デジタルでしか出来ない表現を何らか織り込みたいと考えています。二万人以上にお集まりいただいて、見ていただければと思いますね。
木下
我々も今回も出展させていただき、DXに関するさまざまなサービスやソリューションをこの場で紹介できればと思います。また、博報堂執行役員でHAKUHODO DX_UNITED担当の青木 雅人が、HAKUHODO DX_UNITEDが考える価値創造型DXの推進について講演でお話する予定です。またデジタル甲子園での新しいエクスペリエンスを設計するお仕事は新しいビジネスの可能性を感じていますので、積極的に関わらせていただけたらと思います。引き続きよろしくお願いいたします。

阪急阪神ホールディングスグループ開発室部長
1989年に阪神電気鉄道株式会社に入社。以来、主に鉄道の電気技術部門にて阪神大震災復旧工事、ICカードシステム導入、阪神なんば線建設などに従事する。2009年からアイテック阪急阪神株式会社東京支社の営業部門にて、鉄道会社向けオープン監視制御システム、列車内防犯カメラシステム、列車在線位置表示スマホアプリなどを関東の鉄道会社に販売する。2020年4月からは阪急阪神ホールディングスのグループ開発室にて、阪急阪神グループ全体のDXを推進している。

博報堂 テクノロジー開発局 博報堂DYホールディングス マーケティング・テクノロジー・センター 開発1グループ グループマネージャー チーフテクノロジスト
2002年博報堂入社。以来、マーケティング職・コンサルタント職として、自動車、金融、医薬、スポーツ、ゲームなど業種のコミュニケーション戦略、ブランド戦略、保険、通信でのダイレクトビジネス戦略の立案や新規事業開発に携わる。2010年より、データ・デジタルマーケティングに関わるサービスソリューション開発に携わり、生活者DMPをベースにしたマーケティングソリューション開発、得意先導入PDCA業務を担当。2016年よりAI領域、XR領域の技術を活用したサービスプロダクト開発、ユースケースプロトタイププロジェクトを複数推進、テクノロジーベンチャープレイヤーとのアライアンスも行っている。また、コンテンツ起点のビジネス設計支援チーム「コンテンツビジネスラボ」のリーダーとして、特にスポーツ、音楽を中心としたコンテンツビジネスの専門家として活動中。

株式会社博報堂DYホールディングス
マーケティング・テクノロジー・センター 開発1グループ
テクノロジスト 兼 株式会社博報堂 テクノロジー開発局 上席研究員
University College London MA in Film Studiesを修了後、2007年に博報堂入社。FMCG領域におけるデジタルマーケティング業務、グローバルPR業務に従事。2018年より現職で、ARクラウドや空間コンピューティング技術などを始めとした生活者との新たなタッチポイントやコミュニケーションを生みうる先端技術の研究を行っている。





