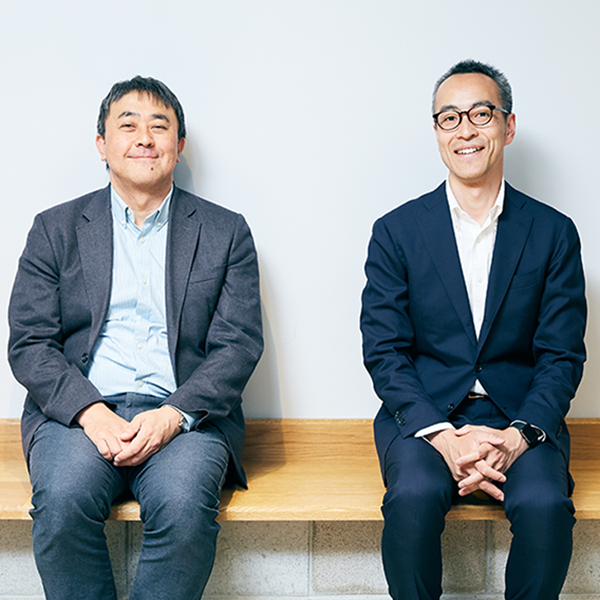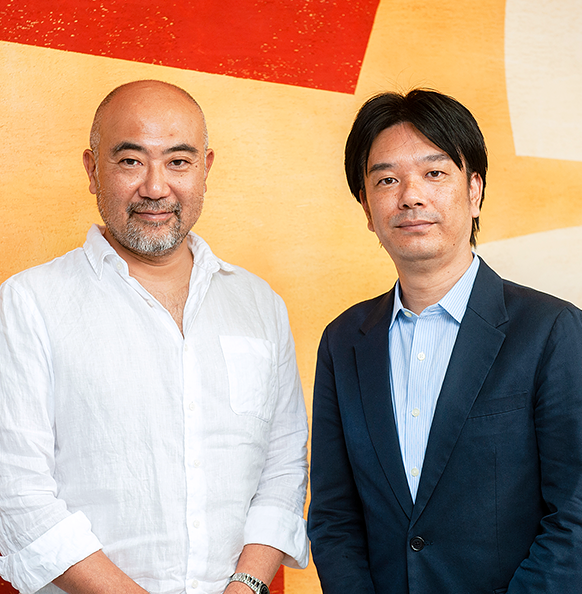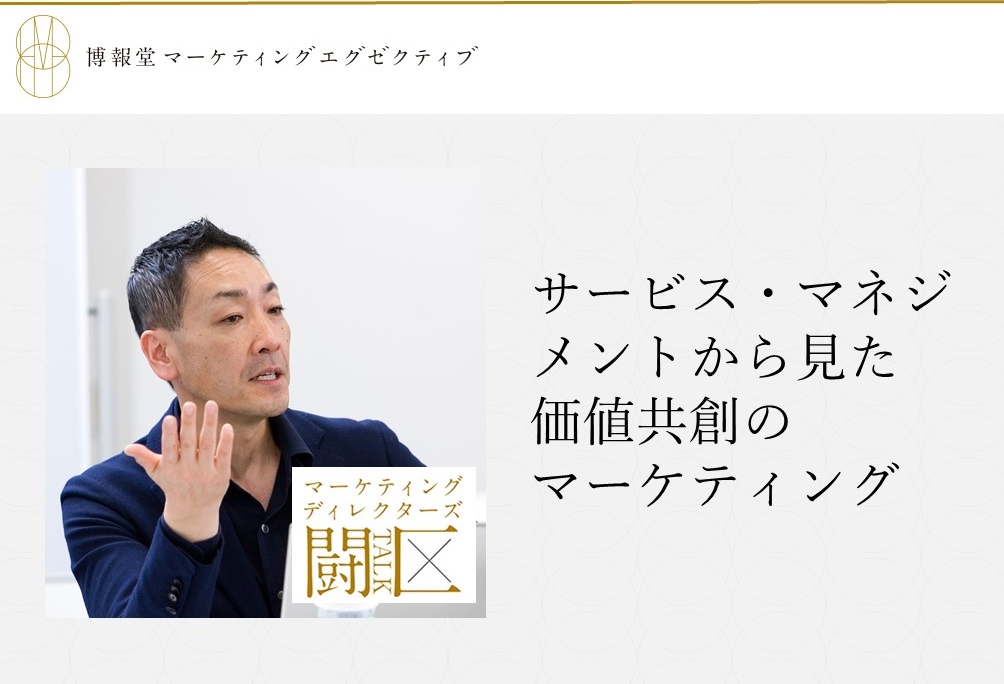
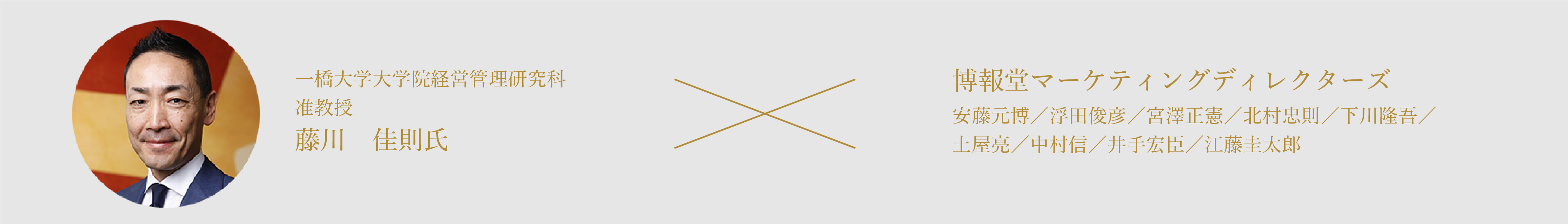
*「博報堂マーケティングディレクター」とは
市場の成熟化と技術革新が交錯する複雑な環境を生き抜くために、これまで以上にマーケティングへの期待が高まっています。
一方で、教科書的なマーケティングの概念では語り尽くせないテーマも増えています。
変化の激しい経営・事業環境と向かい合いながら、マーケティングを進化させて、その新しい可能性、拡張性をリードしていく。
そんな活動をしているのが「博報堂マーケティングディレクター」です。
サービス・マネジメントが提唱する3つのレンズ
博報堂MDr. 今回の闘区のテーマは「サービス・マネジメント」です。いわゆる第3次産業という意味でのサービス業はすでに世界GDPの約3分の2を占め、さらに製造業のサービタイゼーションも進んでいます。藤川先生はサービス・マネジメントのご専門の立場から、現在直面している構造変化の本質は、価値づくりの地平が変わっていることであると指摘されていて、大変興味深いと思いました。価値の生まれる場所が変われば、我々のマーケティングのあり方も本質的な変革が求められるからです。
しかし一方で、日本のあらゆるビジネスの発想は依然としてモノづくりがベースとなっていて、企業も我々マーケターも、そこからなかなか抜けられないという現実がある。これはおそらく根深い問題です。改めて、サービスの本質とは何なのか。価値づくりの構造変化をどう捉えればよいのか。それがビジネスモデルや競争戦略、マーケティングにどのような変革を促しているのか。藤川先生との議論を通じて、マーケティングの未来像をサービスマネジメントの観点から解き明かしていきたいと考えています。
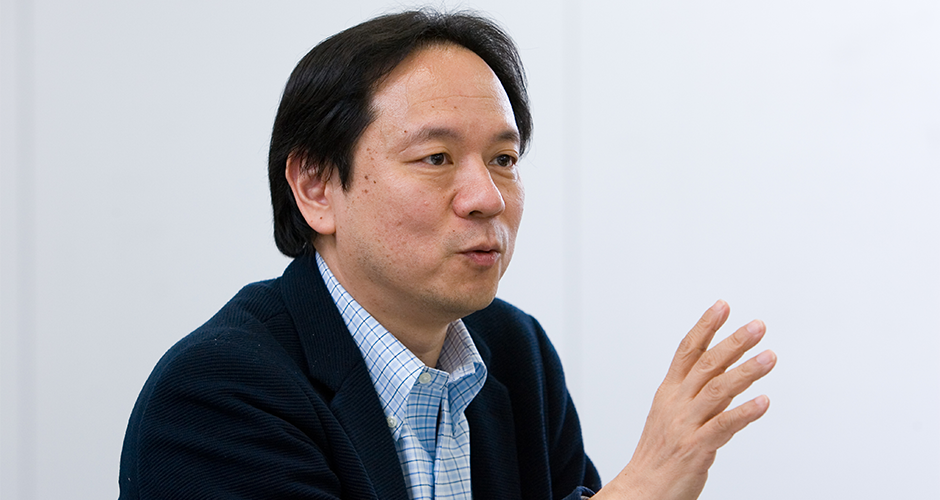
藤川 たしかに今、価値づくりにおいて大きな構造変化が起こっています。
これは仏アバス・メディアの上級副社長を務めていたTom Goodwin氏も指摘していることですが、例えば世界最大の宿泊サービスを提供しているエアビーアンドビーは、自前の不動産を所有していませんね。かつては「ホテルを持たないホテル会社」など考えにくいものでしたが、今では当たり前に存在している。同様にフェイスブックは毎日膨大なコンテンツが生成される世界最大のソーシャルメディアでありながら、自社ではコンテンツをつくっていません。価値づくりを考える上では、こうした先進企業のビジネスモデルを的確に捉える必要があります。
私は世の中の事象を捉える視点やフレームワークを「レンズ」というメタファーで表現しています。我々が今直面しているのは、地殻変動と呼べるほど巨大な地球規模の構造変化です。世界の景色が変わっているのに古いレンズをかけたままでは、見えない部分がどんどん増えてしまう。
従来型のレンズの代表例が「バリューチェーン」です。上流工程から下流工程へ、企業の所有する資産を組み合わせて商品を作り込み、最終的に顧客に届けるまでのプロセスを、価値付与の連鎖として捉える。このレンズが前提としているのは、価値を生み出すのは企業であること。そしてモノやサービスを販売する時点で価値づくりが終わるということです。しかし先ほどのエアビーアンドビーのビジネスモデルでもわかるように、価値を生み出しているのは企業だけではないし、販売は価値づくりの終点でもない。
博報堂MDr. プラットフォーマーのビジネスモデルだけでなく、製造業のサービタイゼーションにおいても同じことが言えますね。
藤川 その通りです。コマツが提供している機械稼働管理システム「KOMTRAX」はその例ですね。ブルドーザーやショベルカーの至る所にセンサーを搭載し、世界中のどこからでも稼働状況を把握できる。例えばアイドリングの時間がどれぐらいかをユーザー企業に伝えることで、建設現場のマネジメントに活かすことができる。商品の販売後に、使用される過程において価値がずっと作られ続けているわけです。
サービス・マネジメントは1980年代に立ち上がった分野です。経営学の中でも戦略論や組織論、マーケティングなどに比べれば遙かに若い学問領域ですが、従来の製造業やサービス業といった産業分類の垣根を超えて、その背後にある価値づくりの論理を明らかにすることを目指して、急速に発展してきました。

モノ(Goods)を価値創造の基本とし、企業が主体となって機能や性能などを付与するかたちで価値をつくり込み、それを顧客に販売する時点において、価値づくりが終了する。このようなモノ主体、企業主体のレンズ1を「グッズ・ドミナント・ロジック」(G-Dロジック)と呼びます。レンズ1を掛けると、市場交換経済を通じて、顧客がその対価を支払う「交換価値」を最大化することが事業のゴールとなります。我々が学んできた経営学の論理の多くは、このG-Dロジックに基づいています。しかし、このレンズではますます価値づくりの全貌を捉えることができなくなりつつあります。
それに対して、2000年代半ばに新たに提唱され、議論が進展する価値づくりのレンズ2が「サービス・ドミナント・ロジック」(S-Dロジック)です。モノ主体ではなく、サービス主体のレンズ。経済活動をすべて「サービス」として捉え、物を介してサービスを提供する企業と、物を介さずにサービスを提供する企業があると考えます。商品・サービスを購買した後の使用段階のおいても価値づくりは続き、そこでは「使用価値」が生成され続けます。レンズ2では、いかに企業と顧客が共に価値をつくっていくかという「価値共創」が重要な課題になってきます。
博報堂MDr. その次に来るレンズ3とは?
藤川 S-Dロジックでは、価値づくりの主体を、「企業」と「顧客」の二者に限定せず、複数のさまざまな主体(アクター)が価値共創に従事する、と考えます。そして、この考え方を的確にとらえるレンズのひとつが、「マルチ・サイド・プラットフォーム」というコンセプトです。たとえば、エアビーアンドビーの場合、個人の借り手と貸し手に加えて、地域のレストランや商店街、観光産業、さらに保険会社なども巻き込んでいます。これらの関係性はBtoCやBtoB、また、CtoCなどといった枠組みでは捉えられません。不特定多数の主体が、いわばAtoA(Actor to Actor)の関係性の中で価値を共創していく。そこで生まれる価値のつながりはチェーンという直線的なメタファーではなく、星座のような多様な連鎖として捉えられます。これを価値星座(Value Constellation バリュー・コンステレーション)と呼んでいます。
博報堂MDr. マーケティングのあり方も、S-Dロジックやマルチ・サイド・プラットフォームの視点から捉えなおして行く必要がありますね。
藤川 はい。G-Dロジックでは、マーケティングの主体は企業、顧客はその客体と考えられますが、S-Dロジックでは、企業も顧客も主体であると捉えます。価値共創を前提とするマーケティングとはどのようなものか。新しいレンズをかけると、どんなマーケティングの姿が見えてくるのか。ぜひ議論していきましょう。

余剰資源・事後創発・価値獲得〜サービタイゼーションを実践する上での3つのカギ
博報堂MDr. マーケティングの未来像の前にまず考えたいのが、企業がレンズ1からレンズ2・3にシフトしていく上での現実的な課題です。サービタイゼーションの潮流を頭では理解していながら、多くの企業がなかなかシフトできないのはどこにボトルネックがあるのか。
藤川 私は3つの要素があると考えています。
1つは、価値を生み出すために必要となる資源の捉え方の問題です。これまで、企業は、自社が所有する資源の希少性によって他社との競争優位性をつくる、と考えられてきました。これに対し、たとえば、ウーバーもエアビーもフェイスブックも自社の資源ではなく、世界中に有り余る顧客が所有する資源を活用して、価値を生み出しています。
老舗のメーカーが、余剰資源を活用することで飛躍している例もあります。その一つがブロック玩具のレゴです。世界中のレゴのユーザーから新商品のアイディアを集めてネット上で公開し、一定数を超える投票があったものを商品化する「レゴアイディアズ」というプラットフォームを2014年から世界展開しています。この取り組みからは、実際にいくつものヒット作が生まれています。レゴ社内には、以前から商品開発チームがありましたが、開発体制をオープンにしたことで、レゴで遊ぶ世界中の億単位の顧客が持つスキルやセンスを活用できるようになったわけです。希少資源ではなく余剰資源を活用する発想が持てるか、そのために外部に向けて組織を開いていくことできるのかがカギになります。
2つめは事後創発、つまりどんな価値を生むのか事前に規定できない状態で意思決定できるかどうかです。前述のコマツ「KOMTRAX」の例も、実際にサービスを開始してみないと企業側も顧客側もどのような価値が生まれ、結果的にどの程度のマネタイズができるのかが予見できませんでした。その全貌がわかっていない段階で、相応の投資を伴うような意思決定ができるか。
3つめは価値獲得、つまりマネタイズポイントをどう設計できるかです。レンズ1のG-Dロジックでは、モノを顧客に販売する時点でマネタイズするしかありません。しかしレンズ2・3を掛けると、価値共創の機会が複数見えてくるので、どこでどうマネタイズするのか、という価値獲得の選択肢も複数持つことになります。さまざまな価値共創と価値獲得の選択肢の中から、何をどう組み合わせるのか、柔軟に設計できるかが重要になります。
博報堂MDr. 今の3つに関係すると思いますが、根強いモノづくり神話は日本において極めて大きなボトルネックではないでしょうか。「日本企業の価値の源泉はモノづくり」「良いモノをつくれば売れる」という意識が、本来多様なはずの価値の可能性を狭めてしまっている。
藤川 たしかにモノづくり的な価値、つまり、販売時点において顧客から対価を得ることで実現する「交換価値」の最大化を追求することで、事業の競争優位を確立することが、かつての日本企業の成功モデルだったのでしょう。意思決定の仕組みや業績評価の枠組み、組織文化などにも深くビルトインしているという面もありますね。

博報堂MDr. 「品質」や「性能」といった意味での「交換価値」ばかりを追求しすぎて、内製化の意識が高くなり、水平分業的な連携ができなくなってしまった。これが企業にとって大きな重荷になっていると思います。
内製化の意識が強いと、外部にある余剰資源を活用する発想にもなかなかシフトできない。先ほどのレゴの例も、自社のモノづくりにこだわりを持ったデザインセンターや開発センターのメンバーが「レゴアイディアズ」のような発想を受け入れるのは容易ではなかったはずです。米国では自社開発主義を戒める「Not Invented Here」という言葉が標語になっていて、自社だけで出来たものがすごいわけではないという考えを浸透させることに時間をかけてきた。日本の製造業も今、自社のモノづくりに対しどれだけ謙虚になれるかが改めて問われているのだと思います。
それともう1つ、自社外からの制約もあります。レンズ1は市場からの評価、株主からの要請にも根強く結びついているので、それに抵抗しない限りレンズ2、3になかなかシフトできないのではないかと。
藤川 それに関しては、ソフトウエア大手のアドビの例が参考になると思います。かつてはパッケージソフトを販売するスタイルでしたが、2012年にクラウドで提供するサブスクリプション型ビジネスモデルへの転換を図ります。パッケージソフトで得ていた定期的なバージョンアップによる収益機会を失ったため、短期的には売り上げが数分の一に縮小したのですね。しかしその一方で、サブスクリプションにより未来の売り上げ予測の確実性が高くなります。そのことを製品市場に対しても資本市場に対しても明確に伝え、顧客の信頼と投資家の納得を得ることが必要となります。同社はそれに真摯に取り組むことで、その後新たな成長段階に入ることができました。
博報堂MDr. たしかに、ビジネスモデルの大きな転換を図ればリスクは避けられない。その先の未来を市場やステークホルダーに如何に信じさせるか。「事後創発」に対するビジョンの明確化とそれを伝えるコミュニケーション力が、突破する力として非常に重要なのでしょう。
藤川 社内外のあらゆるアクターがかけている古いレンズを、新しいレンズに変えようと提言できるのはトップマネジメントだけです。その能力が重要になるのでしょう。
モノ起点からプロジェクト起点へ マーケティングはどう変わるのか
博報堂MDr. 従来のモノ中心の価値づくりが大きく変わるとき、マーケティングはどう変わるべきか。藤川先生は「マーケティングの民主化」というキーワードを挙げていますね。
藤川 はい。先ほどもお話した通り、従来のマーケティングにおいては、企業がその主体であり、顧客はその客体として捉えられてきました。たとえば、「セグメンテーション」や「ターゲティング」など、マーケティングの主要概念には、それを行うのは企業であり、顧客はその対象物である、という前提が色濃く反映されていると思います。しかし今ではマーケティングの全プロセスの中に、顧客が入り込んでいる。たとえば、SNSを利用して「いいね」ボタンをクリックした瞬間に、図らずも、マーケティング活動を担っていることになります。
他方で、例えば米アップルがメーカーでありプラットフォーマーでありリーテーラーでもあるように、業界という概念も融解しつつありますし、むしろ業界の垣根をあえて越えていくことでビジネスチャンスが生まれている。「顧客=ターゲット」ではなく、業界の垣根も無いとなると、業界や市場がそこにあることを前提とするセグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングというSTPマーケティングは限界があるでしょうし、従来とは異なるアプローチが求められているのだと思います。
博報堂MDr. これもモノづくり神話と関係するかもしれませんが、マーケティングにおいても「モノ」を起点にした発想からどれだけ脱却できるかが重要なカギになると感じます。というのも、G-DロジックからS-Dロジックに変わったとしても、引き続きモノは存在するからです。ビジネス環境が構造変化し、サービスや価値共創が重要になっていると言っても、モノ中心の価値づくりを前提としている限りマーケティングプロセスは変わりにくい。
我々が最近心がけているのは、製品提案ではなく「プロジェクト」の提案です。マーケティングをモノからスタートせず、ターゲットも定めない。どれだけ世の中にとって価値あるプロジェクトを提案できるか。そのプロジェクトの価値に対して誰が賛同してくれるか。そして、賛同してくれる生活者や他の企業と一緒に如何により良いプロジェクトをつくっていくか。こうした発想に立たないと、マーケティング活動が本質的には変わらないのではないかと思うのです。

藤川 「プロジェクト」を価値共創の主眼に置く発想はわかりやすいかもしれませんね。
レンズ2・3では、社会の主体すべてをアクターとアクター(AtoA)の関係で捉えます。アクターが担うのはそれぞれがもつ資源の統合(リソースインテグレーション)です。すべてのアクターがいろんなリソースを持ち寄り、くっついたり離れたりしながら異なるリソースが統合されて、さまざまな価値共創をしていく。
博報堂MDr. あらゆるアクターをつなぎながら、プロジェクト全体をどう設計するかが企業活動の中核になりつつあるということですね。「さまざまなアクターと一緒に何をつくっていくのか」をコントロールする営み・試みであると。
その中でマーケティングの重要な役割は、プロジェクトの全体設計をサポートすることかもしれません。生活者はもちろん、企業内の直接関わらない人も巻き込んでリソースインテグレーションし、プロジェクトとして浮かび上がらせていく。
藤川 まさに先ほどご紹介した「価値星座」に通じる話ですね。バリューチェーンをベースにするのではなく、プロジェクトをベースに価値のコンステレーションの創造を目指すのが、新しいマーケティング活動の一つのあり方なのでしょう。
博報堂MDr. 「マーケティングの民主化」とは非常に興味深い表現で、それは新しいレンズをかけることでマーケティングの可能性が広がっていくことだと感じました。プロジェクトや価値星座、アクター全体を俯瞰的に捉える視点や新たな時間軸の観点が、これからのマーケティングに求められていくのでしょう。
さまざまなアクターとリソースインテグレーションしていく中では、当初は想定していなかった価値創造や価値獲得のヒントが見えてくる場合もあるでしょう。従来のマーケティングはターゲットを決めて市場を創出していくという一方向だけに向かいがちでした。今後はもっと柔軟になるべきで、事前計画的ではなく事後創発的に価値創造や価値獲得をするためには、それに合った組織に再編していくことも必要となります。価値共創のマーケティングとは、マーケティングのあり方を本質的に問うことにつながりますね。
profile
藤川 佳則(ふじかわ よしのり)
一橋大学経済学部卒業、同大学院商学研究科修士。ハーバード・ビジネススクールMBA(経営学修士)、ペンシルバニア州立大学Ph.D.(経営学博士)。ハーバード・ビジネススクール研究助手、ペンシルバニア州立大学講師、オルソン・ザルトマン・アソシエイツ(コンサルティング)、一橋大学大学院国際企業戦略研究科 専任講師、准教授を経て現職。
博報堂マーケティングディレクターズ

安藤元博

データドリブンマーケティング局
浮田俊彦

宮澤正憲

北村忠則

下川隆吾

土屋亮

中村信

井手宏臣

江藤圭太郎