博報堂ブランドデザイン・宮澤が考えるブランディングとは?―全4回連載コラム
(Kellog BusinessStyle Japanコラム 「グローバル・リーダーの視点」より転載)
→第一回「ブランディングはどこへ行くのか (1) ブランディングとは何をすること?」
◆はじめに
みなさんは“ブランディング”と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか?
私が卒業したノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院は、特にマーケティング分野で有名で、卒業後にマーケティング関連のビジネスに携わる人が多数います。そんなケロッグの卒業生と同様に、私も、ブランドコンサルティングという領域を専業として仕事をしています。
そんな私から見た最近のブランディングについて連載しています。前回は、ここ数年の間にブランディングの定義や守備範囲が大きく変化してきている、ということを書きました。今回は、ブランディングのやりかた、すなわち「手法の変化」についても述べてみたいと思います。
曖昧になりつつある境界線その1~企業の外側と内側
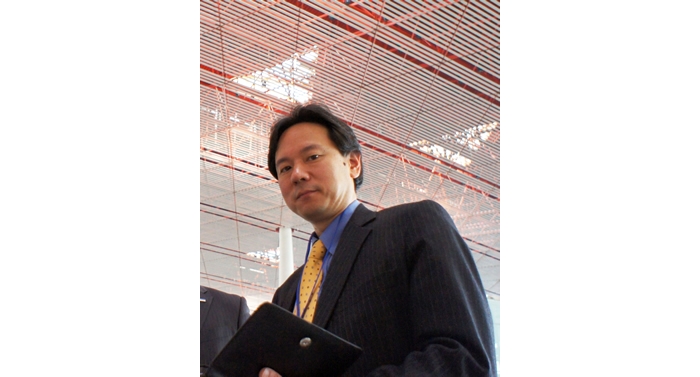
ブランディングの作業は、多くの場合、部門横断型のプロジェクトとして進められます。これはブランディングがマーケティング部門だけの業務ではなくなり、開発、企画、営業、人事など多数の関連部門にわたる全社的な業務となったためです。
さまざまなバックグラウンドの関係者が集まることから、プロジェクトの進行は、互いの考えを理解し合って一緒に解決策を考えていけるワークショップ形式で行う場合がほとんどです。私の部署だけでも、クライアント企業に対して、昨年一年間で300回以上のワークショップを開催しました。ほぼ毎日どこかで行っているくらい、ブランディングにおけるワークショップは定番の手法になっているともいえます。
さらに最近では、その企業の社内のメンバーだけでなく、社外関係者や顧客、一般生活者などを交えたワークショップも頻繁に実施しています。これは、「マルチステークホルダー型ワークショップ」と呼ばれています。
私の部でも、昨年から東京大学教養学部と連携して、一般企業人が東大生とオープンに共創しながら一つのブランドをつくりあげる「ブランドデザインスタジオ」という授業プログラムを実施しています。これもマルチステークホルダー型ワークショップの一つの例です。
この手法の良いところは、ブランドの活動を検討するときに、社内だけの視点に偏った議論にならずに、最初から社外の意見を積極的に取り入れることができるところです。背景や知識の異なる人々に同じ場で議論してもらうため、進行にはコツがいりますが、うまく機能すると社内と社外の人々の意見が融合され、とても活発な対話が展開されます。こうしたワークショップが成功すると、社外の人がまるで社内の人のように意見を述べてくれます。よって、プロジェクトの途中から、誰が企業の中の人で、誰が外の人かわからなくなってくるというシーンもよく見られます。
このように、企業がよりオープンになることで、インナー(社内)とアウター(社外)の境目が曖昧になってくる、そんな新しいやり方が増えてきているのです。

曖昧になりつつある境界線その2~プロセスの川上と川下

ブランディング手法の変化は、消費者調査方法にも表れています。一昔前は、グループインタビューや定量調査といった形で生活者の声を聞くことが一般的でした。しかし、最近はそうした伝統的な手法よりも、ニューロリサーチや深層心理調査、またエスノグラフィーといった新しいタイプの調査を用いるケースが多くなってきました。
なかでも最近注目されている手法として、MROC(Marketing Research Online Community)というものがあります。MROCとは、あるテーマや特定のブランドに関して興味関心のある人を集め、オンライン上でさまざまな対話を繰り返しながら、新しい発見やアイデアを引き出していく手法です。
MROCにはリサーチという言葉が含まれるため、一見するとオンライン上のグループインタビューのようにも見えますが、本質的には異なります。対象者は比較的長い期間(1カ月~半年)の間、特定のブランドやテーマについて企業担当者を交えて対話を続けます。そのため最初は調査対象者として参加してもらっていますが、最終的にはそのブランドのファン、もしくはその企業の開発メンバーの一人のような感じに変化していくのが面白いところです。
MROCにはリサーチという言葉が含まれるため、一見するとオンライン上のグループインタビューのようにも見えますが、本質的には異なります。対象者は比較的長い期間(1カ月~半年)の間、特定のブランドやテーマについて企業担当者を交えて対話を続けます。そのため最初は調査対象者として参加してもらっていますが、最終的にはそのブランドのファン、もしくはその企業の開発メンバーの一人のような感じに変化していくのが面白いところです。
似たような手法としては、大学や研究開発の領域で主に導入されている「オープンラボ」というものがあります。幅広い関係者を巻き込んで研究を進めるこのような活動自体は以前からありましたが、こちらもここ1~2年で活発になっています。さらに、企業の中では、競合との関係などから長らく閉鎖的で共創とは無縁であった研究開発部門を思い切ってオープンにし、広く世の中から知見を募集するという新しい動きがみられ、注目を集めています。
従来のブランド開発のプロセスは、上流工程から下流工程へと川のように流れていました。現在でも多くの企業で、技術開発や製品開発といった川上側の作業と、広告・広報といった川下側の作業は明確に分かれていると思います。ところが、MROCのような共創型手法が導入されると、製品開発に意見を述べた生活者は開発メンバーの一員でありながら、商品が世に出ると今度はそのまま口コミで情報を発信してくれる広報メンバーの一員にもなるわけです。そして世の中の評判や感想を、再び開発側にフィードバックしてくれます。つまり、従来分離していた川上と川下が、生活者を通じてぐるっとまわった円環構造になってきているのです。
従来は閉鎖的であった開発チームが、よりオープンになることで、企業に根強くあった川上と川下という境目もまたどんどん曖昧になってくる、そんな時代が来ています。
曖昧になりつつある境界線その3~情報の送り手と受け手
さらに最終的なコミュニケーションにおいても、ブランディング手法は変化しています。最大の変化は、言うまでもなくソーシャルメディアの登場です。FacebookやTwitterに代表されるSNS(ソーシャルネットワークサービス)の利用者はいまや4000万人以上ともいわれ、もはや立派な“マス”といえます。そのため、ブランドコミュニケーションにおいて、SNSの活用は当たり前になっています。
ソーシャルメディアの特性については、さまざま語られていますのでここでは省略しますが、ソーシャルメディアは従来のマス広告とは異なる性質を持っています。ブランディング的な視点で見ると特に興味深いのは、送信者と受信者の関係が曖昧になることでしょうか。テレビCMや新聞広告では、明確に情報の送り手側(企業側)と、それを見る受け手側(生活者側)がはっきり分かれていました。しかし、生活者も積極的に情報発信をしているソーシャルメディアにおいては、その区別は曖昧です。
例えば、ある新ブランドが市場に導入され、広告が流れたとします。それを見たAさんが気に入ったとSNSにコメントします。Aさんは、広告を見た時点では情報の受け手側でしたが、コメントを書き込んだ時点で、情報の発信側にまわっています。そして、Aさんのコメントを見た友人Bさんがまた同様のコメントをすると、このときBさんから見るとAさんはまるで企業の広報のような役回りですし、好感を持ったBさん自体もそれをコメントすることで今度は情報発信側にまわっています。
つまり、発信者と受信者の関係もまた、曖昧になってきているのです。

企業と生活者の間の垣根をなくし、オープンな関係を築く
こうして見てきたように、ブランディングの領域には日々新しい手法が生まれ、企業と顧客の境界線といった今まで明確に存在したさまざまな境界線を曖昧にする、あるいは曖昧化を加速するという現象が起きています。
前回の最後にも書きましたが、共創型の「オープン・ブランディング」は、企業と顧客を対等な立場として進めていきます。どちらが上でも下でもありません。生活者は調査の“対象者”ではなく“協力者”であり、情報の“受信者”ではなく“発信者”ととらえます。顧客を大切な“仲間”ととらえ、さまざまな対立概念と思われるものを融合させながら一緒に力を合わせてブランドをつくっていく、そんな新しいプロセスです。
企業の外側と内側を隔てる垣根をなくし、企業と生活者が対等な関係になっていく。オープン・ブランディングの“オープン”なる所以は、ここにあります。
しかし、企業と生活者が対等な関係になるといっても、そんなに簡単にできることなのでしょうか? 次回は、オープン・ブランディングの難しさについてです。




