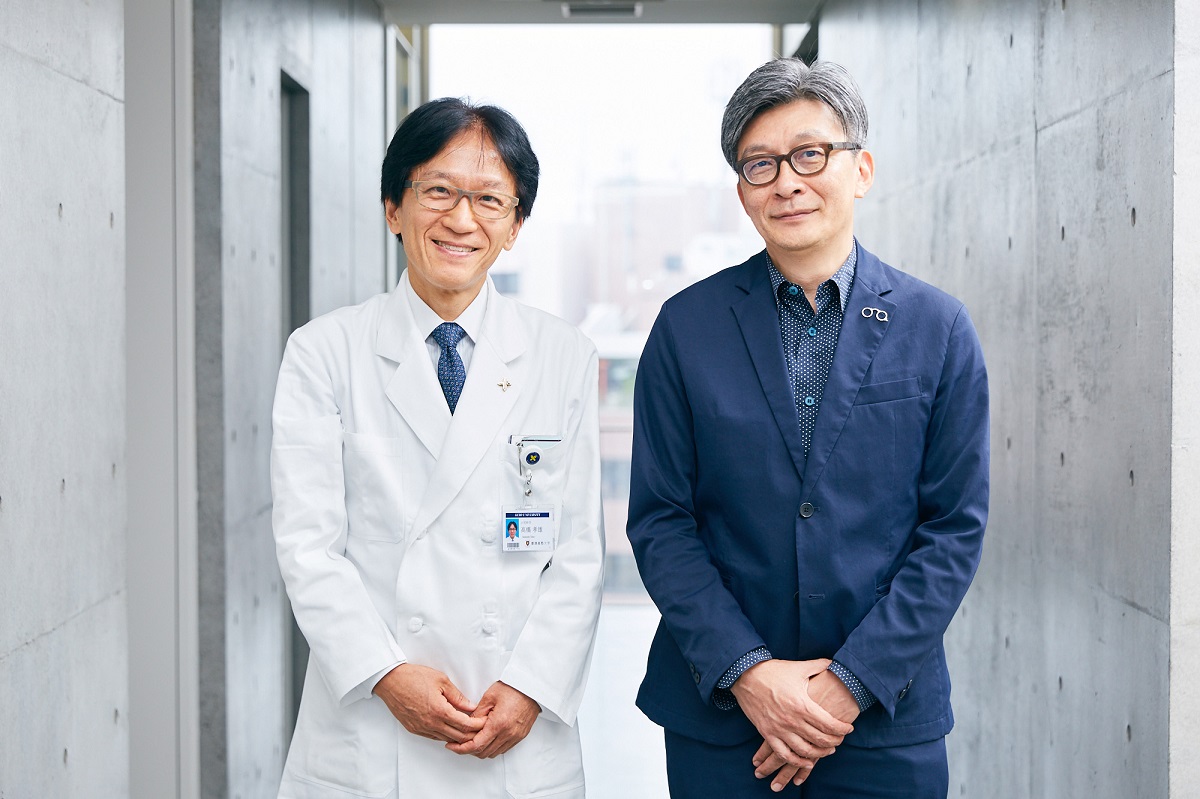
命を助ける医療ではなく、命を授ける医療
深谷 高橋先生は慶應義塾大学医学部の小児科教授であり、さらに日本小児科学会会長も務められています。縁あって、私は2014年から同学会の広報委員会の外部委員を担当させていただいていて、それからのお付き合いになります。
地方にとって「少子化」や「医療」はとても大きいテーマです。高橋先生と出会ってから、この問題を小児科医のお立場からどう捉えられているのか、ずっと興味を持っておりました。そこから、地域の課題を克服する新しいヒントが見えてくるかもしれません。先生とお話ししながら探っていければと思っています。
そもそも高橋先生は、初めから小児科医を目指していたのですか?
高橋 いえ、きっかけは偶然でした。医学生だった頃、臨床実習で産婦人科に配属されていた時のことです。指導を受けていたドクターの受け持ち患者さんが、妊娠28週で緊急に分娩しないと赤ちゃんの命が危ない事態となり、僕も立ち会うことになったんです。当時の医療レベルでは、妊娠28週で産まれた赤ちゃんの生存率は今に比べてだいぶ低いものでしたから、おじけづくような気持ちでした。
深谷 かなり厳しい出産になりそうだなと。
高橋 はい。でも、いざ分娩室に入ってみると独特の活気にあふれていました。3人の新生児専門の小児科医が立ち会っているという安心感もあってか、お母さん自身も想像していたよりも落ち着いた様子でまわりのスタッフに話しかけていました。
ようやく産まれた小さな赤ちゃんはぐったりしていて、産声もあげず、体は赤黒い状態でした。すぐに口から気管に管を入れて人工呼吸を始める。すると、さっきまでぐったりしていた赤ちゃんのからだ全体が、瞬く間に明るいピンク色に染まりました。その時、心臓がしっかりと動きだしたのだと思います。新しい命がスタートした瞬間ですね。
しかもそこにいた小児科医たちは、命を左右する重大時にもまったく冷静で、まるでF1レースでピット作業に携わるクルーたちのように、一瞬一瞬にプロフェッショナルとしての技を発揮していました。「お母さん、赤ちゃん、お預かりしますね」「よろしくお願いします!」そんなやり取りに心を奪われたのかもしれません。
そこで僕が見たのは「命を助ける医療」ではなく、「命を授ける医療」でした。小児科医の役割の尊さと、プロとしての格好良さに本当に感動しました。おそらくあの経験が、この仕事に携わるきっかけになったのだと思っています。

深谷 とても感動的なエピソードですね。
エピソードといえば、以前先生からお聞きした「小児科医は、子どもの病気を診ることだけが仕事ではない」というお話も印象的でした。病気だけを診ても、その子を幸せにはできないのだと。病気の時もそうでない時も、その子のことを丸ごとすべて診る。仮にお腹が痛くても、子どもはそのことを的確に伝えられないかもしれない。だからお母さんやお父さんからも話を聞かないといけない。その際に家族機能、つまり、子どもが育つのに適切な環境が用意されているかどうかにも目を配る。子どもと家族に寄り添うのが小児科医の役割なのだと。
高橋 その通りです。僕は「背景にこそ真実はある」と思うのです。子どもの病気には必ず背景がある。本当に治さなければいけないのは病気自体ではなく、病気に至ってしまう背景です。「総合診療医」であるばかりでなく、僕たち小児科医の仕事は「総合医」です。この言葉には、病気を「診療する」だけでなく、その「背景」に関わっていくという意味合いがあります。総合診療医であることは総合医であるための条件のひとつに過ぎません。
子どもの病気の大多数は自然に治る。つまり自然治癒力に任せればいいケースが大半なわけです。風邪などはもちろん、インフルエンザだってクスリ無しでも大抵は治ります。それほど子どもたちの自然治癒力は素晴らしいものです。
しかしその一方で、子ども自身の治癒力では絶対に克服できないものもある。わかりやすい例としては虐待やいじめであったり、あるいは極度に貧困な家庭で育っている場合などです。子どもはその環境が当たり前と感じているから、自分の健康や権利が害されていると自覚できないし、口にも出せない。真の背景に切り込んで、子どもたちを救うためには、小児科医の「総合医」としての目が不可欠なんです。
小児科医に求められる代弁者としてのコミュニケーション
深谷 我々が携わっている広告やマーケティングも、突き詰めれば人と人をつなぐコミュニケーションの仕事です。お聞きしていると、医療の現場でもかなり高度なコミュニケーションがなされていると感じます。情報の摂取の仕方も、発信のあり方も。
高橋 高度なコミュニケーションかどうかはわかりませんが、患者さんやそのご家族が診察室に入った瞬間の表情とか、どんなふうに歩いて椅子にどう座ったとか、医師である私との距離感とか、それらを観察するところから診療行為が始まるのは事実です。むしろそこが主要な診療行為です。聴診器を当ててから背景にある何かに気づくようでは遅い。
小児科医に求められるコミュニケーションのキーワードは、「代弁者」であることだと思います。病院に来た子どもたちが、自分の状況についてうまく表現できずにいる。言葉だけでなく、表情や立ち振る舞いから本当の症状や感情までも読み取って、それをわかりやすい言葉に翻訳して返してあげる。
「泣いているのは、お腹が痛いからじゃないね。白衣の先生たちがちょっと怖いんだね」
「こんなに痛いのに、お母さんに“大丈夫!”って言われたのが悲しいんだね」
その先の診断や治療については基本的にガイドラインがありますから、AI(人工知能)やロボティクスに任せてもいいぐらいです。でも複雑な背景を推察する能力は、現状のAIにはないでしょう。診療の現場でこういうやり取りができると、そこに信頼感が生まれます。人の話を深掘りして聞きながら目と心も配る「傾聴力」と、それを分かりやすく正確な言葉に翻訳し、プロとしての判断つまり診断とか治療について、子どもやご家族に納得したと感じさせる「説得力」。具体的にはこの2つが代弁者に求められる力です。
深谷 そのような良い代弁者であるために、診療中に先生が大切にしていることはなんでしょうか?

高橋 一言ではなかなか言えないんです。傾聴力といっても単に相手にしゃべらせればいいというものではない。医療の現場では限られた時間のなかで、できるかぎり正確な情報がほしい。例えば、お母さんが「風呂場で子どもが火傷をしました」と言っている。それではつじつまが合わない。その違和感を感じ取ることが大事です。それに気づかないと、虐待を見逃してしまう。聴くことによって正しい情報だけを得ることが重要です。そこに意識を集中すると話の聞き方も自然と変わってくるんです。
理屈ではなくて、実体験を通じて失敗を重ねないと正しい情報とそうでない情報が見分けられない。正しい情報だけを聴きだせるようになるだけでも5年以上はかかるのではないでしょうか。さらに、限られた時間の中で、こちらが必要としていることだけを話すように促せるようになるには10年以上の実地経験が必要ではないでしょうか。
僕自身、過去30年以上の小児科医としての人生のなかで、虐待の結果残念ながら亡くなってしまったお子さんや、子を残して自死を選んでしまった若いお母さんなど、辛い見落としをいくつか経験してきました。代弁者としての経験を積み重ねていないと、本質的な背景を捉えることはできないと思います。
地域の医療と小児科医
深谷 地方の問題について少し話させてください。日本は課題先進国と言われますが、地方ではその課題がより深刻で、特に少子化が重くのしかかっています。地方の少子化について、小児科医としてどう捉えていますか。
高橋 地域が100年先まで生き残るためには、そこに幸せな子どもたちがいる必要があります。子どもがいるということは、その親世代である若い夫婦が暮らしていて、働ける場所があるという証拠です。地域社会を維持するためには子どもが健康に育つことが必須で、これを僕は地域のバイタルサインと呼んでいます。体温や血圧、呼吸や脈拍が人間の生命活動の証であるのと同じように、子どもが生まれ、健康に育っているかが地域にとってのバイタルサインなんですね。地方創生にはさまざまな取り組みがありますが、そこにもし子どもに対する施策が抜け落ちていたとしたら、その地域社会は長くは存続できないでしょう。
産科と小児科は「政策医療」と呼ばれます。国が存続するためにどうしても必要な医療です。少子化が進んでついに子どもが産まれなくなったら、いずれその地域は滅びてしまう。100年後も存続するつもりでいるならば、産科と小児科、初等教育が政策的に維持されなければなりません。

深谷 国や自治体に対して、何らかの政策提言などはなさっているのですか?
高橋 はい。その1つが中核病院の整備と病院の機能分担です。かつては地方でも中小規模の病院が乱立していました。それぞれの地区で子どもの健康を守るために病院の確保がなされた結果です。しかし、24時間体制の小児医療を維持していくためには小児科医の数が全く不足している状況で、そのような医療体制を見直す必要が出てきました。高度な小児医療を提供するための中核となる病院を決めて機能集中を行い、それ以外の病院やかかりつけ医の先生方との連携を格段に強化したんですね。一定規模の自治体の中核病院については、採算はさておき、産科と小児科を維持するために皆が力を合わせる。一方で、中小の病院や診療所については、そこで行われる基本的な小児医療のレベルをしっかり維持して、さらに上げていく。高度な小児医療も大切ですが、かかりつけのお医者さんって非常に重要なんです。患者さんやそのご家族に最初に接する代弁者ですから。
深谷 私も以前、地域の医療機関の整備計画をお手伝いしたことがありますが、人材をどう確保するかでどこも頭を悩ませています。そもそも今、日本では小児科医の人材は減っているんでしょうか。

高橋 意外とそうでもないんですよ。実態を調べてみると、小児科の専門医試験を受ける人の数や、小児科学会に入会する医師数などを見ると、毎年500〜600人ぐらいで、ほぼ横ばいで推移しています。増えてはいないけれど、減ってもいない。私の体感的にも、新たに小児科医を目指す医師がどんどん減っていくという気配は感じません。小児科医になる人は、はじめから小児科医を目指しているケースが多いのかな。
深谷 地方で小児科医になる人の数はどうですか。
高橋 東京・大阪をはじめとする5大都市圏で小児科医になる人と、それ以外の道府県で小児科医になる人、その数の比はだいたい50:50で、これもあまり変わらない。年を追うごとに小児科医が大都市に集中してきている、というわけでもないんです。
深谷 なるほど、興味深いですね。
高橋 結局、好きで選んだ仕事だから。どんなに大変でもみんな誇りを持ってやっていて、辛いからと言って小児科医を辞める人はほとんどいません。私自身も小児科医を辞めたいと思ったことは一度もないです。
ただし今後の課題として、小児科医の育成強化とレベルアップは重要です。今はちょうど医療の潮目が大きく変わりつつある時期です。感染症の患者が激減している一方で、虐待や摂食障害、貧困や母子の精神的ケアなど、今まで見落とされてきた問題が浮き彫りになってきた。医療全般に言えることですが、特に小児科医は、見落としてはいけない問題が変わってきたんですね。
だから、僕らのような先輩医師が、過去の経験に基づいて若い医師を教育することはなかなか難しい。僕らも含めて、小児科医は新しい世代の小児医療を学んでいかなければならない。
少子化や病気の種類の変化の結果、一人ひとりの子どもやそのご家族に今までよりは時間をかけることができるようになるはずです。子どもは地域のバイタルサインです。それを途絶えさせないためには、小児科医自身も考え方をリセットしなくてはならない。ちょうどその切り替え時期なんだと思います。
深谷 最後に、地域創生に携わる方々にアドバイスをいただけますか。
高橋 地域社会を維持していくために、広い意味での「子育て」を大切にしていただきたいです。ご自身が結婚・出産するかどうかとは無関係に、子どもたちの代弁者になる機会はいくらでもあります。その土地で幸せに育って、楽しい想い出がたくさんあれば、大人になって一時的に都会に出たとしても、生まれ育ったところにきっと戻ってくるでしょう。そして地元でまた子どもを産んで幸せに育てていく。それを地域のみんなで見守ってほしい。子どもたちが地域の未来を支えていくんだという気持ちを持っていただきたいなと思います。
対談を終えて|深谷信介
神の領域
テンポよく、お話し上手で、熱意漲る立ち振る舞い
そんな高橋先生のホームグラウンドである研究室にはじめて伺った日は、とても穏やかな日和
いつも頼りっぱなしの高校総代の親友から、珍しくこの頼みごとを聞いたのは5年ほど前。1つ恩返しができるかもしれない、迷いながらもそんな気持ちで日本小児科学会広報委員会の委員を引き受けることにしたあの日もとても穏やかだった
外科や内科・眼科に歯科に耳鼻科・・・
専門医が多く、大人になると全体から部分が切り離れていく。
小児科医は、総合医。ひとの総体を診る。
「は~い、どしたのかな?」
先生の柔和な問いかけに、場が和む。
子どもも親も親戚も、病気以外のことも、日々のくらしも、家族関係も
言葉にもならない、あらゆる情報を瞬時に正確に読み解いて、
子どもを核に献身的にそのコミュニティ総体に向き合う。
背景にこそ真実がある
聴診器を当ててから背景にある何かに気づくようでは遅い
私では到底受けきれない、計り知れない重みのメッセージ
30年以上、日々いのちとくらしに寄り添い圧倒的な現場を活きる高橋先生からの、表層化する社会に対する奥深き視座が脳裏に焼きついている
瞬時に、しかも丸ごと、どれだけのことを読み解けるか?
地域も全く一緒
表層的な情報戦争に一喜一憂し
次々と生まれるプラスチックワードに振り回され
経緯や文脈や背景という時空間を失っていく地域、社会、くらし
子どもは社会の宝
子どもを診ることはサービスではない、まして業でもない
ほんとうの人は、ほんとうの何かをいつもいつでも診つづけている
国を支え国をつくる政策医療の最前線で陣頭指揮を取り続ける高橋先生、
ほんとうにありがとうございました
これからも、子どもたちを・家族を・日本人を・日本という国を・どうぞよろしくお願いいたします
プロフィール

慶應義塾大学医学部小児科教授/医学博士/日本小児科学会会長。
1957年生まれ。1982年慶応義塾大学医学部卒業。1988年から米国マサチューセッツ総合病院小児神経科に勤務、ハーバード大学医学部の神経学講師も勤める。1994年帰国。慶應義塾大学医学部小児科において医師、教授として活躍中。著書『小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て』がベストセラーに。

スマート×都市デザイン研究所長 / 博報堂ブランド・イノベーションデザイン副代表
事業戦略・新商品開発・コミュニケーション戦略等のマーケティング・コンサルティング・クリエイティブ業務やソーシャルテーマ型ビジネス開発に携わり、都市やまちのブランディング・イノベーションに関しても丸ごと研究・実践を行う。主な公的活動に環境省/環境対応車普及方策検討会委員 総務省/地域人材ネット外部専門家メンバー、千葉県地方創生総合戦略策定懇談会委員、富山県富山市政策参与、鳥取県琴浦町参与(内閣府/地域創生人材支援制度派遣)なども請け負う。








